ご覧いただきありがとうございます。
「CFP合格への道」シリーズとして、各科目の勉強方法について詳しく書いていきます。
第5回目は「リスクと保険」です!この分野は何と言っても資料の読み取り力が試される分野になります。
これまでの記事は過去記事から!CFP全体の方法については過去記事をご覧ください。

CFP合格への道 ⑦ラリスクと保険の出題範囲
出題範囲を過去のデータからまとめると、以下の通りです:
1. リスクマネジメント
- リスクの概念(純粋リスクと投機的リスクなど)
- リスクマネジメントのプロセス
- 保険の基本原則(大数の法則、収支相等の原則など.
2.生命保険
- 生命保険の種類(定期保険、終身保険、養老保険など)
- 保険料の仕組み(純保険料・付加保険料)
- 契約者・被保険者・受取人の関係
- 生命保険の税務(保険料控除、保険金の課税関係)
- 生命保険商品の選び方とプランニング
3. 損害保険
- 火災保険・地震保険の仕組み
- 自動車保険(自賠責保険と任意保険)
- 傷害保険・賠償責任保険
- 損害保険の税務と契約内容の見直し
4. 第三分野の保険(医療・介護・年金保険)
- 医療保険・がん保険・介護保険の仕組み
- 公的医療保険・公的介護保険との関係
- 個人年金保険の種類と税制
5. 公的保険制度
- 公的年金制度(国民年金・厚生年金)
- 公的医療保険制度(健康保険、後期高齢者医療制度)
- 労災保険・雇用保険
6. 企業のリスクマネジメントと保険
- 企業向けの生命保険(経営者保険、事業保障)
- 企業の損害保険(PL保険、施設賠償責任保険)
- 役員・従業員向けの保険制度(福利厚生)
7. 保険関連の法律と規制
- 保険業法・消費者契約法・金融商品取引法
- 生命保険募集人・損害保険募集人の規制
- 保険契約者の権利と義務
過去5年間の平均合格率は37.0%です。
リスクと保険は前半が生命保険に関する問題、後半が損害保険に関する問題と分かれているのも他の科目と違って独特です。また単なる計算問題ではない資料の読み取りが中心になっています。
CFP合格への道 ⑦リスクと保険の勉強方法
リスクと保険は2日目の1科目目09:30~11:30となります。
同日にタックスプランニングと相続事業承継があるので、2科目ずつ受験するスケジュールであれば1日目の科目と組み合わせるか、同じ日にある親和性の高いタックスプランニングと合わせて受けても良いでしょう。(交通費と時間の節約にもなりますね!)
ではどのように勉強するのか見ていきましょう!
1.約款の効率的な読み取りをマスターしよう。
リスクと保険は「時間配分」がめちゃくちゃ重要です。
過去問を開いてみると…問題の長さ(約款)に度肝を抜かれます。保険会社にお勤めであれば約款に見慣れているので、全てを読み込まなくても回答できるかもしれません。ですが、私のように保険会社勤務経験も約款を見たこともない人間からすると時間がかかります。何度も過去問を解きながらら「何が問われていて、どこに書いてあるのか」「ひっかけはないか」を素早く理解するようにしましょう。
2.各商品・制度について理解しよう!
本試験においては、多くの種類の商品が登場します。「定期・終身・医療・がん・収入保障・変額・外貨建て」等基本的な商品の特徴と付随して「各商品を活用した相続対策」についても勉強しましょう。個人だけでなく法人保険の仕分けもありますので、個人法人しっかり分けて理解を深めていきましょう。
3.損害保険もぬかりなく
損害保険には「住宅・火災・地震・自動車・傷害等」個人に係るものは馴染みがあるかもしれません。一方で、法人に係るもの「労働災害・使用者賠償責任・PL等」は日頃触れることはないので勉強のためと割り切って覚えましょう。
合格への道 ⑦まとめ
ご覧いただきありがとうございました。
今回は「リスクと保険」にフォーカスして勉強方法を解説しました。
私は過去問以外に、ネットや店頭で保険商品のパンフレットを貰い約款になれることを徹底しました。
慣れてくると、全部読み込まなくてもピンポイントで答えにたどり着くことができます。
またリスクと保険もタックスプランニングと親和性が高いので、上述したように余裕がある人はタックスプランニングと合わせて学ぶといいでしょう。限られた学習時間の中で効率的に進めましょう。
次回は最後【相続・事業承継】の勉強方法や勉強時間について公開予定です。
個別相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
セミナ開催情報! 毎月第3水曜日(昼・夜)開催!
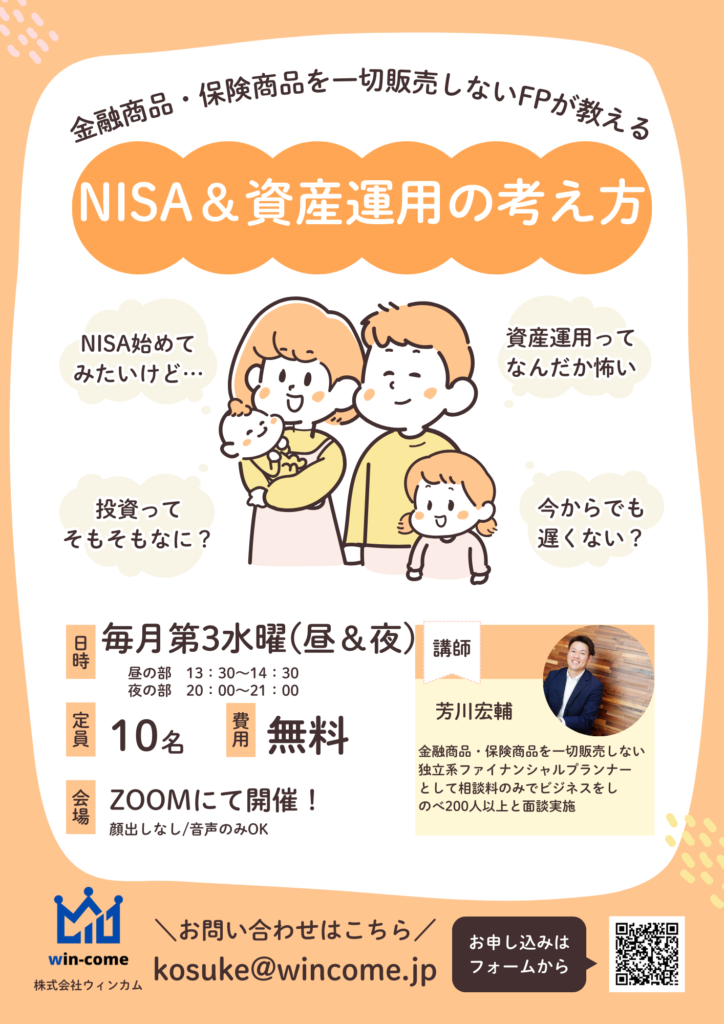

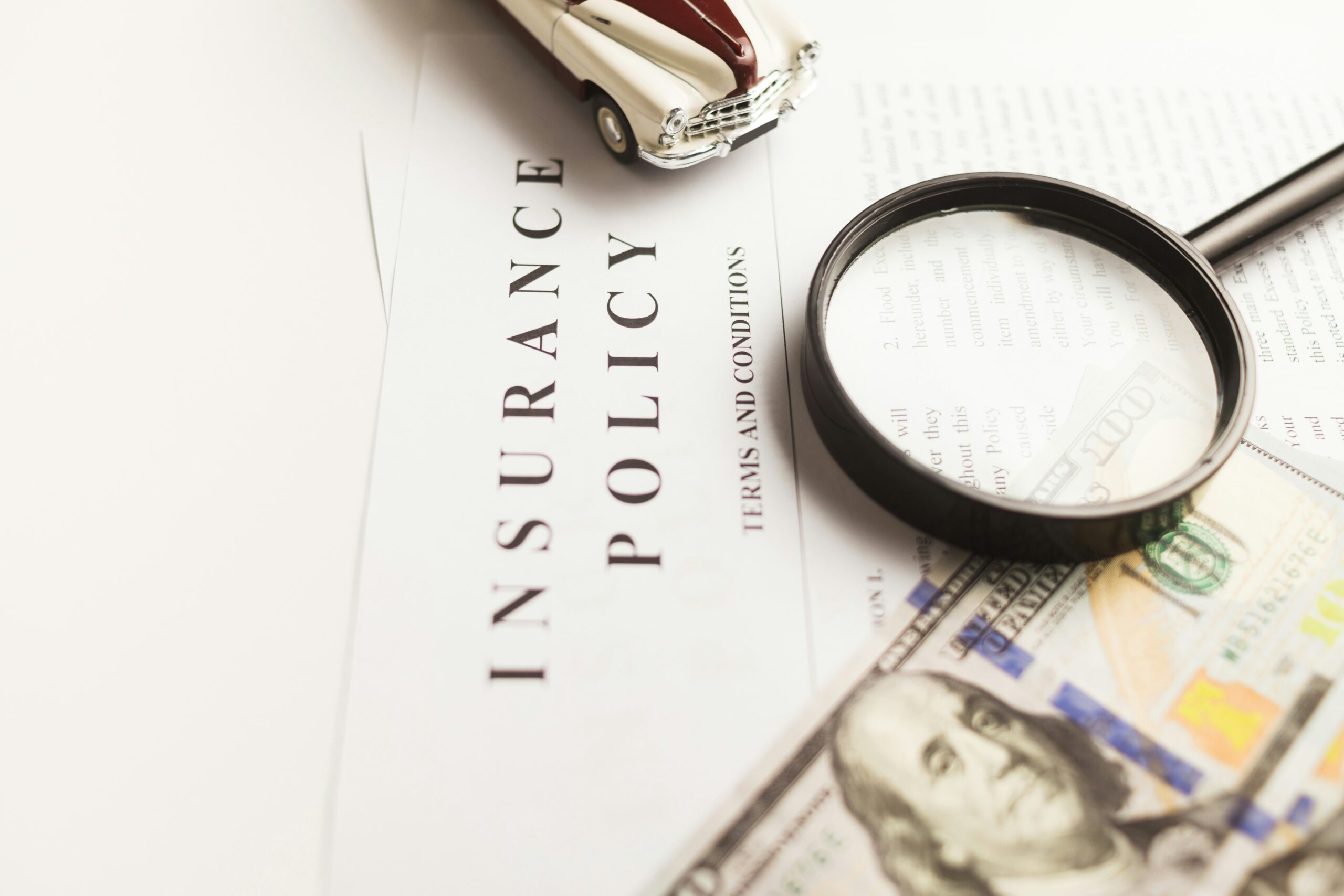
コメント